事業部制組織とは、本社機能の下に事業内容ごとに分割された「事業部」を配置し、各事業部が自律的な意思決定と経営責任を担う組織形態です。多角化・拡大する企業において本社負担の軽減、迅速な意思決定、経営者人材の育成、各事業の利益責任の明確化といったメリットがある一方、各事業部での資源の重複やサイロ化(縦割り意識)による非効率、事業部間の対立などのデメリットも存在します。
特徴
- 自己完結型組織:各事業部には、研究開発、生産、営業、販売など、その事業を遂行するために必要な機能がすべて備わっており、独立した組織として機能します。
- 利益責任の所在:各事業部が自らの事業の損益に対する責任を持つ「独立採算制」が採られます。
- 専門性の発揮:事業ごとに部門が細分化されているため、それぞれの事業の専門性を活かした経営が可能です。
- 迅速な意思決定:事業の状況に応じて、各事業部が独自の判断で意思決定を行えるため、スピード感のある経営を実現できます。
メリット
- 本社機能の負担軽減:本社は個別の事業運営に深く関与せず、企業全体の経営戦略や投資判断に集中できます。
- 意思決定のスピードアップ:各事業部が迅速な判断を下せるため、市場の変化や顧客ニーズへの対応力が向上します。
- 経営者人材の育成:各事業部を独立した経営者として運営することで、将来の経営を担う人材を育成できます。
- 経営成果の可視化:事業部ごとに損益が管理されるため、どの事業が利益を上げているか、あるいは不振なのかが明確になり、経営資源の選択と集中がしやすくなります。
デメリット
- 資源の重複・非効率:各事業部が独自の機能を持つため、重複する部署やリソースが生じ、経営資源の無駄が発生する可能性があります。
- サイロ化(事業部間の壁):各事業部が独立しすぎると、組織全体での連携が希薄になり、異なる事業部間の協力や情報共有が難しくなり、新たなアイデアが生まれにくくなることがあります。
- 事業部間の競争・対立:独立採算制のため、各事業部間でリソースや業績を巡る対立が起きやすくなります。
- 経営資源の偏り:収益性の高い事業(花形事業)に資源が集中し、収益性の低い事業(窓際事業)がさらに資源不足に陥るなどの格差が生まれることがあります。
編成手法
事業部制には主に以下の3つの編成手法があります。
- 製品別::製品やサービスの種類ごとに事業部を編成します。
- 地域別::特定の地域ごとに事業部を編成します。
- 顧客別::特定の顧客セグメントや属性ごとに事業部を編成します。

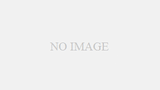
コメント