ポーリングとは、複数の機器やプログラムが連携して動作する際に、主となるシステムが他のシステムに対して定期的に状態を問い合わせることで、データの送受信や処理を同期させる方式のことです。
ポーリングの概要:
- 仕組み:親機(ホスト)が子機(端末)に対して、定期的に「何かデータはあるか?」「処理は完了したか?」などと問い合わせることで、データの送受信や処理のタイミングを制御します。
- 特徴:
- 一定の間隔で問い合わせを行うため、プログラミングが比較的容易です。
- 通信経路が一本しかない場合でも、データの送受信の競合を防ぐことができます。
- 端末側は、問い合わせがあるまで待機する必要があるため、タイムラグが発生する可能性があります。
- 利用例:
- ネットワーク監視(サーバーの死活監視など)
- プリンターやスキャナーなどの周辺機器との連携
- メインプログラムとサブプログラム間の連携
- 携帯電話の着信や、リモコンのボタン操作など
死活監視
死活監視とは、システムやネットワーク機器が正常に動作しているかを継続的に監視する行為です。
※詳しく知りたい方はこちら
- ポーリングの種類:
- 監視のためのポーリング:機器の状態を定期的に確認し、異常を検知する。
- 検出のためのポーリング:データの送信や処理の完了を待つために、定期的に問い合わせる。
ポーリングと関連用語:
- トラップ:ポーリングとは逆に、機器が状態変化を能動的に通知する方式。
- SNMP:ネットワーク機器の状態を監視するために用いられるプロトコル。
- ICMP (Ping):ネットワークの疎通確認に用いられるプロトコル。
ポーリングのメリット:
- 競合の回避:複数の機器が同時にデータを送信しようとするのを防ぎます。
- リソースの効率的な利用:必要な時だけ通信を行うため、無駄なリソース消費を抑えられます。
- 安定した動作:定期的な問い合わせにより、システムの安定稼働を維持できます。
ポーリングのデメリット:
- タイムラグ:問い合わせがあるまで待機する必要があるため、即時性が求められる処理には不向きです。
- 負荷:頻繁にポーリングを行うと、ネットワークやシステムに負荷がかかる可能性があります。
ポーリングは、ネットワーク監視や機器連携など、様々な場面で利用されている重要な技術です。状況に応じて、ポーリングと他の方式(トラップなど)を使い分けることで、より効率的なシステム運用が可能になります。

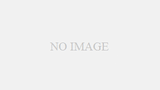
コメント