RISCとは「縮小命令セットコンピュータ」のことで、プロセッサの設計思想の一つです。命令セットを単純化し、固定長の短い命令を多数実行することで、高速処理や効率的な電力利用、設計の簡素化を目指します。これは、複雑な命令を扱うCISC(命令セットコンピュータ)に対する対義語として提唱されました。
RISCプロセッサの特徴
- シンプルな命令セット: 命令の総数を減らし、一つ一つの命令を単純な処理に限定します。
- 単純な処理の組み合わせ: 複雑な処理は、複数の単純な命令を組み合わせることで実現します。
- 固定長の命令: 命令の長さを固定することで、命令の解釈を高速化し、パイプライン処理を容易にします。
- パイプライン処理: 複数の命令を段階的に並行して実行する「パイプライン処理」に適しており、実質的に1命令を1クロックサイクルで実行するのと同等のスループットを実現します。
- レジスタ中心の演算: 演算の基本をレジスタ間で行い、メモリへのアクセスはロード/ストア命令に限定します。
- パイプライン処理との関連性: パイプライン処理を効率化するため、演算に使うレジスタの数を多く備えています。
RISC-Vについて
近年、注目を集めているのが、カリフォルニア大学バークレー校が開発したオープンソースの命令セットアーキテクチャ(ISA)であるRISC-V(リスクファイブ)です。
- オープンソース: ライセンス料が不要で、誰でも自由に設計や利用ができます。
- エコシステム: 仕様策定やプロセッサ開発、ソフトウェア開発など、急速にエコシステムが拡大しています。
- 用途: IoTデバイスや組み込みシステム、研究分野などでの採用が活発化しています。

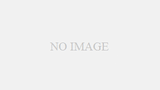
コメント