NAND型フラッシュメモリは、東芝(現 キオクシア)の舛岡富士雄氏が発明した、電源がなくてもデータを保持できる不揮発性メモリの一種です。NOR型と比べて回路規模が小さく、安価に大容量化でき、書き込みや消去も高速であるため、SSD、USBメモリ、SDカード、スマートフォンなどに幅広く利用されています。データアクセスはブロック単位で、ランダムアクセスは遅いですが、大容量データ保存に適しています。
特徴
- 不揮発性:電源がオフになっても記憶したデータを保持できます。
- 大容量化と低コスト:回路規模が小さく、集積化しやすいため、大容量化しても比較的安価に製造できます。
- 高速な書き込み・消去:NOR型フラッシュメモリよりも書き込み・消去が高速です。
- 不向きな点:1ビット単位の直接的な読み取り(ランダムアクセス)は遅く、ブロック単位でのアクセスとなります。
- 高耐久性:振動や衝撃に強く、消費電力も低いという利点があります。
補足
データの書き込み及び読み出しはページ単位、データの消去はブロック単位で行います。
用途
NAND型フラッシュメモリの主な用途は以下の通りです。
- SSD:パソコンの記憶装置として利用され、HDDに代わる高速なストレージとして普及しています。
- USBメモリ、SDカード、メモリーカード:デジタルカメラやスマートフォンなどに使用されるデータストレージです。
- スマートフォン、携帯音楽プレーヤーなど:これらの電子機器の内部記憶装置として搭載されています。

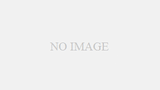
コメント