DRAMはコンデンサに電荷を蓄えてデータを保持するため低コスト・大容量ですが、定期的なリフレッシュ動作が必要で速度は遅いです。一方、SRAMはフリップフロップ回路を使用するためリフレッシュが不要で高速ですが、回路が複雑でコストが高く、DRAMより容量は小さくなります。DRAMはメインメモリ、SRAMはCPUキャッシュなど、それぞれの特性を活かした用途で使われています。
リフレッシュ動作・・・DRAM(Dynamic Random Access Memory)などにおいて、コンデンサに蓄えられた電荷が自然放電によって失われるのを防ぎ、情報を維持するために、一定時間ごとにその電荷を補充する動作のことです。
DRAM (Dynamic RAM)
- 仕組み:コンデンサに電荷を蓄えることでデータを記録します。
- メリット:
- 低コスト・大容量::構造が単純なため、容量あたりの単価が安く、高密度なデータ保存が可能です。
- デメリット:
- リフレッシュ動作が必要::コンデンサから電荷が漏れるため、データの保持には一定時間ごとに内容を書き直すリフレッシュ動作が必要です。
- 速度が遅い::リフレッシュ動作や構造の制約により、SRAMより読み書き速度が遅くなります。
- 主な用途:パソコンのメインメモリ(主記憶装置)など、大容量のデータ処理が必要な場所。
SRAM (Static RAM)
- 仕組み:フリップフロップ回路を使用し、電流の流れ方でデータを保持します。
- メリット:
- 高速アクセス::リフレッシュ動作が不要なため、データの読み書きが高速です。
- 低消費電力::データを保持する際の消費電力がDRAMより少なくなります。
- デメリット:
- 高コスト・小容量::回路が複雑で集積化が難しいため、容量あたりの単価が高くなります。
- 主な用途:CPU内部のキャッシュメモリなど、高速なデータアクセスが求められる場所。

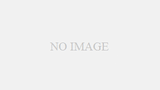
コメント